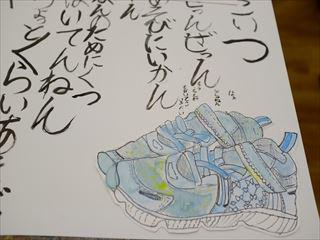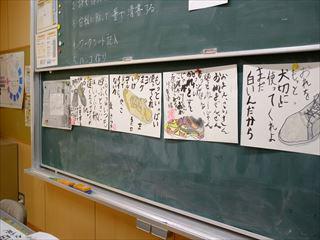公益財団法人尼崎市文化振興財団主催の「おでかけアルカイック アウトリーチ事業」を5・6年生対象に実施しました。
オーボエ奏者の大島弥州夫さんとピアニストの大西隆弘さんが、成文小学校まで来てくださって音楽室でミニコンサートが行われました。
 |
 |
演奏曲は『オーボエ・ソナタ 第1楽章 K.374d/モーツァルト』、『エリーゼのために/ベートーヴェン』、『ミュージカル「レ・ミゼラブル」より「夢やぶれて」/シェーンベルク』、『涙そうそう/BEGIN』、『オーボエ・ソナタ 第1楽章 K.13/モーツァルト』の5曲でした。
 |
 |
コンサート後半は、質問コーナーがあり、子どもたちからのさまざまな質問におふたりが答えてくださいました。
授業後の子どもたちからの感想には「演奏しているピアノ、オーボエのきれいな音、迫力のある音が混ざり、とってもきれいだったのが印象に残っています」「ピアノとオーボエだけでとても美しい音楽が演奏できることに感動しました。それから2人のタイミングとかも合っていて、すごいと思いました」ということばが見られました。
演奏が始まると音楽室の空気が変わりました。
普段の授業でも、子どもたちに感動を与えられるような授業ができたらいいなと感じる時間でした。

 5・6年出前授業(おでかけアルカイック)
5・6年出前授業(おでかけアルカイック)